最近、「日本生まれの赤ちゃんの3%が外国人」というニュースを目にしました。
一見すると、ただの統計のようにも思えます。けれど私は、その言葉に小さな違和感を覚えました。
なぜなら、「日本生まれ」なのに「外国人」と強調することで、どこか“外側”の存在のように扱ってしまっているように感じたからです。
それは意図していなくても、聞く人によっては差別的な印象を受けかねません。
「3%」という数字の裏にあること
報道によれば、2024年に日本で生まれた赤ちゃんのうち約2万人が外国籍だったそうです。
母親の国籍は中国、フィリピン、ブラジルなどが多いとのこと。
これはグローバル化が進む日本社会を反映しており、特別なことではありません。
むしろ注目すべきは「外国人が増えている」ことではなく、多様な文化を持つ家庭が日本で子どもを育てている現実です。
その背景には、国際結婚、留学、労働、避難、さまざまな理由があります。
数字はその多様性を示すサインであって、“問題”ではありません。
もし立場が逆だったら
想像してみてください。
もし日本人が海外で子どもを産み、その国の新聞に「この国で生まれる赤ちゃんの〇%は外国人」と書かれていたら、どんな気持ちになるでしょうか?
「自分の子が“この国の子ども”ではないように扱われた」──
そんな悲しさや距離感を感じる人も多いはずです。
だからこそ、私たちも同じ想像力を持ちたい。
日本で生まれた子どもたちは、この国で育つ“未来の住民”です。
国籍よりも、「どんな環境で安心して育てるか」を考えることが大切です。
本当に必要なのは“支援”と“理解”
数字を並べるよりも、次のような支援をどう整えるかが問われています。
- 母子保健や健診の多言語対応
- 学校・保育園での日本語サポート体制
- 医療現場での通訳や文化的配慮
- 地域での相談窓口や孤立防止の取り組み
これは“特別な支援”ではなく、誰もが安心して子育てできるための社会の基盤づくりです。
メディアと言葉の責任
言葉は、見えない線を引くことがあります。
「外国人の赤ちゃん」よりも「海外にルーツを持つ子どもたち」と表現するだけで、印象は大きく変わります。
報道の自由は大切ですが、同時に「どう伝えるか」という姿勢も問われます。
数字を伝えるなら、定義や背景も一緒に伝える。
“話題”ではなく、“理解”を広げる報道こそ、これからの時代に求められるものです。
まとめ
日本で生まれ、日本で育っていく子どもたち。
その小さな命に、国籍という壁は必要でしょうか。
「日本で生まれてくれてありがとう」
「この国で元気に育ってほしい」
そう思える社会であってほしい。
数字の前に“人”がいる──その当たり前を、私たちはもう一度思い出すべきだと思います。
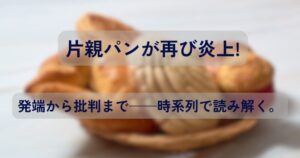


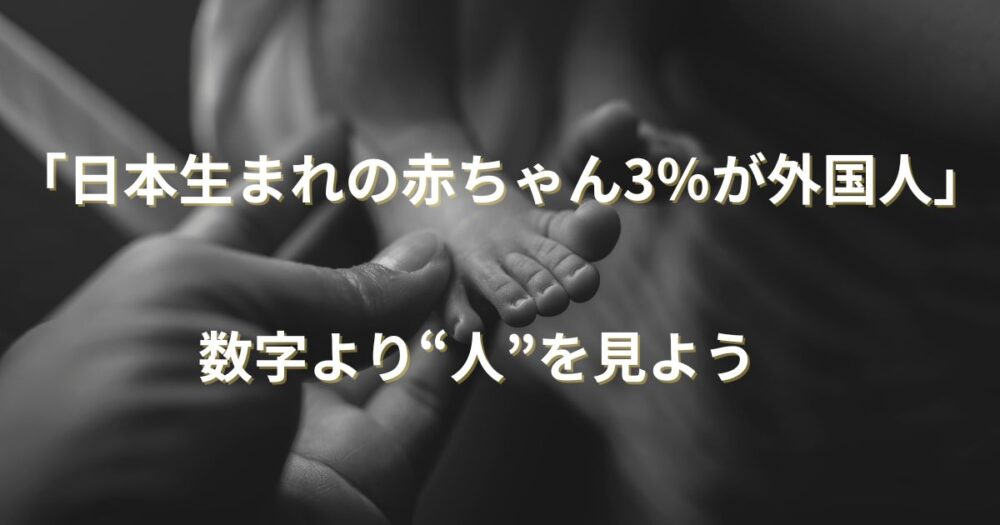
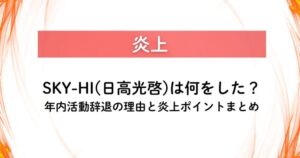
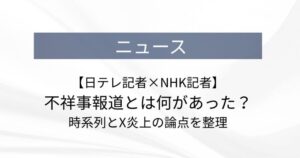
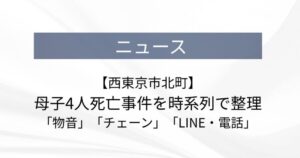
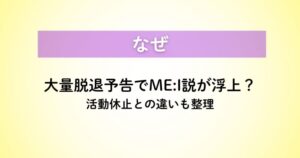
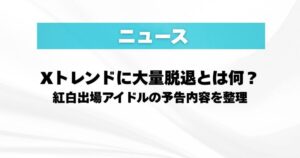
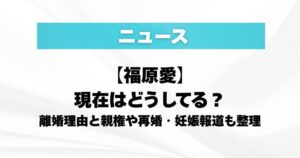

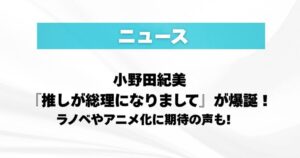
コメント