「白井球審」と検索するとあわせて「誤審」「クビ」といったかなりきつめの言葉が出てきて、
ギョッとした方も多いのではないでしょうか。
試合中の判定をめぐってSNSが炎上したり、過去のシーンが切り取られてショート動画で拡散されたりと
白井一行球審は何かと“話題になりやすい審判”として名前が上がりがちです。
一方で、NPBから公式に高い評価を受けている現役トップ審判の一人でもあります。
この記事では
- 「白井球審 誤審」「白井球審 クビ」と検索されてしまう背景
- なぜトラブル視されやすいのか
- それでもNPBからはきちんと評価されている事実
といった点を感情論だけに流されずに整理していきます。
白井球審はベテラン審判で「アーイ」のコールが名物
6/7 甲子園
— まさ (@057JKotf55lrGVv) June 7, 2025
白井球審の所作が良い#白井一行 pic.twitter.com/Ls3euUFKjr
まず前提として「白井球審」と呼ばれているのはNPB(日本野球機構)所属の審判員・白井一行(しらい かずゆき)球審のことです。
- 29年目のベテラン審判員(2025年時点)
- 主に球審としてマスクをかぶることが多い
- ストライク判定のときの甲高い声での「アーイ!」というコールがトレードマーク
この甲高いストライクコールは、「審判の中で最も声が大きい」と評されるほどで
2018年にはその存在感や姿勢が評価され「審判員奨励賞」に選ばれています。
テレビや球場で観ていてもすぐに「あ、白井球審だ」とわかるくらいの個性派審判。
この“良くも悪くも目立つスタイル”が、後で触れる「トラブル視されやすい」というイメージにもつながっている部分がありそうです。
「誤審」と言われるようになったきっかけ
佐々木朗希投手とのシーン
「白井球審 誤審」というワードが強く意識されるようになったきっかけの一つが、
2022年4月24日・オリックス対ロッテ戦(京セラドーム大阪)で起きた出来事です。
この試合で先発していたのは、完全試合達成直後で大きな注目を集めていたロッテの佐々木朗希投手。
2回の投球判定に不満そうな表情を見せた佐々木投手に対し白井球審が険しい表情でマウンドへ歩み寄り、
捕手の松川選手が慌てて間に入る。
というシーンが中継で映し出されました。
この一連の場面が
- 中継映像や配信の“切り抜き動画”としてSNSに大量にアップされる
- 「詰め寄りすぎでは?」「あの対応はどうなのか」と大きな論争になる
- 「白井球審」「白井球審 佐々木朗希」といったワードがトレンド入りする
といった形で一気に拡散され、白井球審の名前が“トラブルの象徴”のように語られるきっかけになりました。
その後、日本野球機構(NPB)は「別の方法がしかるべきだった」としつつも白井球審への処分は行わない方針を示しています。
この件をきっかけに
白井球審 = 選手に詰め寄る審判
白井球審 = 問題を起こす人
といったイメージがかなり強くついてしまった印象は否めません。
なぜ「クビ」とまで検索されるのか
さらに物騒なのが「白井球審 クビ」という検索ワードです。
これには、おおまかに次のような流れがあると考えられます。
- 判定に納得できなかった一部のファンが感情的になって
「クビにしろ」「二度とマスクをかぶるな」といった強い言葉を書き込む - そうした表現がSNSや掲示板で繰り返し使われる
- 検索エンジンがそれを拾い関連ワードとして表示してしまう
つまり「クビ」という言葉は公式な情報ではなくあくまで感情的な批判から生まれたワードだと考えるのが自然です。
実際には
- 白井球審がクビになったという事実はない
- むしろ2025年には最優秀審判員賞を受賞している
という状況なので検索ワードと現実の評価の間にはかなりギャップがあります。
ネット上の強い言葉がそのまま“検索ワード”として定着してしまう典型例と言えそうです。
白井球審が「トラブル視」されやすい背景
ここからは、もう少し俯瞰して
「なぜ白井球審だけ、ここまでトラブル視されやすいのか」
という点を整理してみます。
① 良くも悪くも「目立つ」コールとジェスチャー
白井球審の大きな特徴はなんといってもあの甲高い「アーイ!」というストライクコール。
- 声が大きく球場中に響き渡る
- 全身を使ったジェスチャーで判定がはっきり伝わる
観客目線ではわかりやすく、エンタメとしても「白井球審の試合は見ていて楽しい」という声もあります。
ただその一方で
- 目立つ分、印象に残りやすい
- 何かあったときに「また白井球審か」と名前付きで語られやすい
という“損な役回り”にもなりがちです。
同じような判定でも地味なタイプの審判より白井球審の方が記憶に残ってしまう。
これは人間の心理としてもどうしても起こりやすい部分だと思います。
② 選手との距離感がクローズアップされやすい
佐々木朗希投手との一件に象徴されるように白井球審は選手に対してしっかりと注意を促す場面もあります。
審判としては
- 試合をコントロールする
- 不満の表現がエスカレートしないようにする
といった役割もあるのである程度の“線引き”は必要です。
ただ、映像で切り取られたときには
- 「高圧的だ」
- 「怒っているように見える」
と感じる人も少なくありません。
一部分だけ見ると「トラブルを起こしている審判」に見えてしまう、そんな“写り方の難しさ”もあるのかなと感じます。
③ SNSやショート動画の「切り取り文化」
近年は、試合中の一場面が
- X(旧Twitter)の短尺動画
- YouTubeショート
- TikTokのクリップ
などで何度も拡散されるのが当たり前の時代です。
白井球審の行動や過去のワンシーンが切り取られてSNSやショート動画で広く出回っていることも
「トラブルが多い」
「問題のある審判だ」
と受け取られてしまう要因になっています。
実際には
- 何事もなく淡々と終わる試合がほとんど
- ミスのない試合や普通の判定はわざわざ切り抜かれて拡散されない
という現実があります。
それでも、派手なシーンだけが何度もタイムラインに流れてくることで「白井球審はいつも何かやっている」というイメージが強くなってしまう。
この“見え方の偏り”は今のネット社会ならではだと感じます。
NPBからは「最優秀審判員賞」に選出
一方で、白井球審は「誤審」「トラブル」と批判されるだけの存在ではありません。
日本野球機構(NPB)は2025年11月17日、2025年シーズンの「最優秀審判員賞」に白井一行審判員(48)を初受賞したと発表しています。
NPBの発表によるとおもな選考理由は
- 29年という長きにわたる審判経験によりリーダーシップやゲームマネジメント力が増したこと
- 判定技術や正確性に安定感があり名実ともにNPBを代表する審判員へと成長したこと
といった点です。
つまり、リーグを運営する側から見ると「技術面・経験・ゲームコントロール能力を含めてトップクラス」と評価されている審判だということです。
ネット上では「誤審」「クビ」といった言葉が目立ちますが、実際には
・2018年に「審判員奨励賞」
・2025年に「最優秀審判員賞」
と、キャリアを通じて着実に評価を積み上げてきた審判員でもあるという事実は押さえておきたいところです。
本当に「誤審が多い」と言えるのか?
ここまでを踏まえてあらためて
本当に白井球審だけ誤審が特別多いと言い切れるのか?
という点を考えてみます。
- 審判も人間でありミスを完全にゼロにすることは不可能
- スロー再生やリプレー検証の発達で昔よりも判定が細かくチェックされる時代
- 「誤審」と断定できるケースは感覚ほど多くない
といった現実を考えると
「白井球審だけが飛び抜けて誤審が多い」ということを示す公的なデータはない
というのが冷静なところです。
そもそもNPBは、審判ごとの誤審率やミスの回数といった細かいデータを一般には公表していません。
むしろ
- 甲高いストライクコールと大きなジェスチャーで目立つ
- 佐々木朗希投手との一件など映像としてインパクトのある場面が何度も切り抜かれている
- 感情的な批判が「誤審」「クビ」といった強い言葉を生みそれがそのまま検索ワードとして残っている
といった要素が重なった結果、「誤審が多い人」というイメージだけが一人歩きしている可能性も大きいと感じます。
個人的には
「誤審かどうか」を断定するよりもなぜそう見られてしまうのか、その背景を知る方が野球の見え方も少し変わる
そんなケースのひとつが白井球審なのではないでしょうか。
まとめ|言葉だけで決めつけず背景も含めて見てみたい
最後に、ポイントを簡単に整理します。
- 「白井球審 誤審/クビ」と検索される背景には、佐々木朗希投手との一件など印象的なシーンの“切り取り拡散”がある。
- 甲高い「アーイ!」コールや大きなジェスチャーで目立つ分、名前が挙がりやすくイメージが膨らみやすい。
- 一方で審判員奨励賞や2025年シーズンの最優秀審判員賞を初受賞するなどNPBからは技術やゲームマネジメント力を高く評価されている。
判定にモヤっとするのはファンとして自然な感情ですが「誤審」「クビ」といった言葉だけで決めつけず
これまでのキャリアや評価も含めて見てみると白井球審の印象も少し変わってくるかもしれませんね。
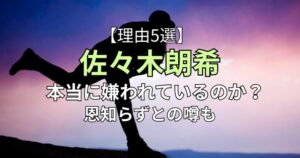
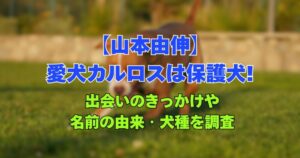
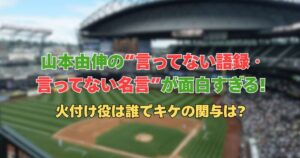

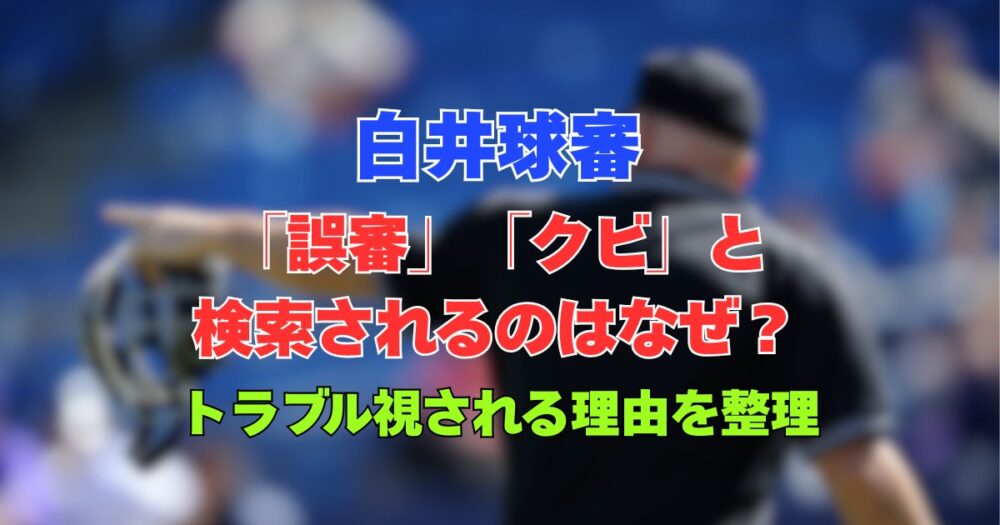
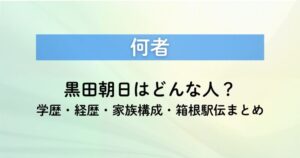
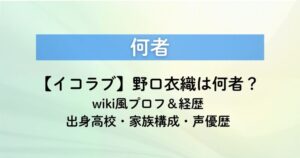
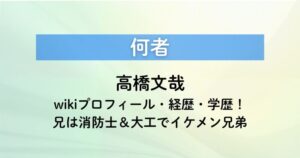
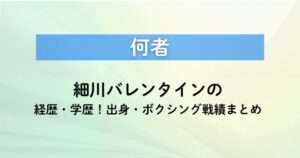
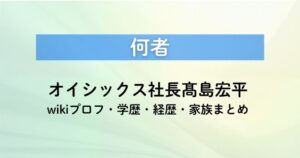
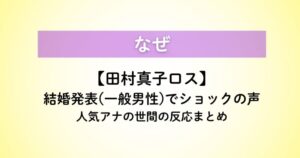
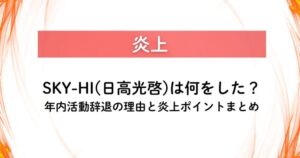
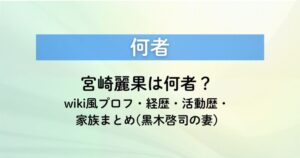
コメント