救急現場では、瞬時の判断と正確な行動が求められます。
その中でも機関員は、周囲の安全確認、隊の動き、傷病者の状態など、広い視野と冷静さが不可欠な存在です。
私が救急車を運転していた頃、意識していたのは『冷静になれる状況を、自ら作ること』でした。
今回は、そのために私が実践していた工夫についてお話しします。
冷静さを保つことは、機関員の仕事の一部
現場に向かう車内、サイレンを鳴らしながら交通の流れを読み、事故を起こさないように走る。
そんな緊迫感のなかで機関員が焦ってしまえば、隊全体の動きにも影響を及ぼします。
逆に、機関員が冷静でいれば、隊長や隊員、場合によっては傷病者や家族まで不思議と落ち着いてくるものです。
だからこそ、私は「冷静であること」は運転技術と同じくらい重要だと感じていました。
とはいえ、私はもともと焦りやすく、パニックにもなりやすい性格でした。
特に緊急走行中は、思いがけない出来事に頭が真っ白になりそうになることも多かったのです。
そんな私を救ってくれた“先輩のひとこと”
あるとき、先輩隊員がふとこんなことを教えてくれました。
「焦りそうになった時、自分が落ち着ける“仕草”を決めておくといいよ」
最初は「そんなことで本当に落ち着けるのか?」と半信半疑でしたが、これが私の転機となりました。
焦りを感じたときに、あらかじめ決めておいた動作を行う。
それによって『自分は落ち着ける』というスイッチが入り、不思議と頭が整理されていくのです。
意識的に繰り返すうちに、やがてその仕草が、私にとっての“冷静さを取り戻す儀式”となりました。
私が選んだ“仕草”とは?
私が実際に取り入れたのは――
『ウィンカーレバーを軽く触る』という行動です。
運転の妨げにならず、誰にも気づかれずにできる。
それでいて、自分の中では『冷静になる合図』として強く意識できる、ちょうどいい動作でした。
焦りを感じた瞬間、そっとレバーに触れる。
それだけで、一呼吸おけるようになったのです。
他にも試してみたい“冷静のスイッチ”
人によって落ち着く動作は違います。私が出会った仲間たちの中には、こんな仕草を使っている人もいました。
- 耳たぶを軽く触る
- 深呼吸を一度だけする
- ハンドルの握りを少し変える
- つま先を少し上げて感覚を切り替える
ポイントは、「この仕草をすれば、自分は落ち着ける」という思い込みを日頃から繰り返し身につけておくことです。
“訓練された習慣”が、いざという時にあなたを助けてくれます。
冷静さは、特別な才能ではない
私が焦りを克服できたのは、才能があったからでも、心が強かったからでもありません。
ほんの小さな“意識と習慣”を、自分の中に育てていっただけです。
「焦っても大丈夫。自分には戻れるスイッチがある」
そう思えるだけで、救急車の運転も、現場での判断も、ぐっと楽になりました。
最後に:冷静さを育てるためにできること
これから機関員を目指す方へ。
また、現役で「自分は焦ってばかりだ…」と悩んでいる方へ。
焦ることは、悪いことではありません。
大切なのは、それにどう向き合い、どう立て直すかです。
あなたにも、きっと“冷静に戻れる仕草”が見つかるはずです。
その小さな行動が、あなた自身を、そしてチームを救ってくれるかもしれません。
↓↓関連記事はこちら↓↓
「精神疾患は甘えじゃない」――元救急隊員が出会った“強すぎた人たち”の真実
【救急隊員・機関員必見】現場で即使える!傷病者情報の整理術とメモの取り方
救急隊で合わない隊員とチームを組んだ時の対処法7選!ストレスを減らすためのコツ






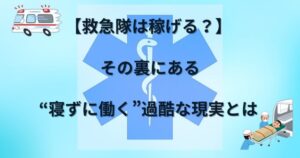
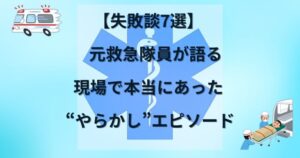
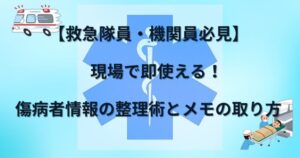
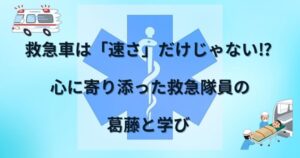
コメント